発達検査や療育を始めて、ようやく少し落ち着いてきたころ。
「保育所等訪問支援」という制度を紹介された。
最初は「保育所って名前なのに、小学生でもいいの?」とピンとこなかった。
でも、実際に支援員さん(療育の先生)が学校へ行ってくれるようになってから、
“学校での困りごと”の見え方が大きく変わっていった。
🌱1. 保育所等訪問支援ってどんな制度?
保育所等訪問支援は、発達面でサポートが必要な子どもに対して
支援員さんが学校(や園)に行き、その子の様子を実際の環境の中で見てくれる制度。
授業中の姿、集団での動き、友達とのやりとり。
普段の教室の中で何が起こっているのかを観察して、先生に助言したり、保護者に共有してくれる。
療育(放課後デイ)みたいに「通った場所の中で練習する」だけじゃなくて、
「実際に困っている場所で、困っている様子を見てくれる」のが大きいところ。
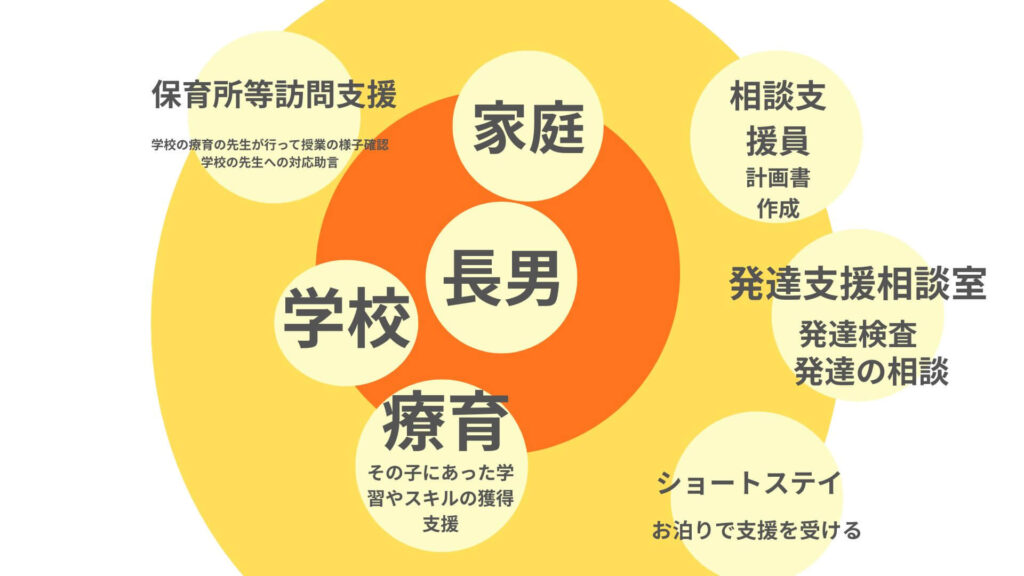
🏛️申請の流れ(うちの場合)
うちの場合はこんな感じで進んだ。
・療育を続けていたときに、先生から「保育所等訪問も合うと思う」と提案を受ける
・自治体の障害福祉課に行く
・すでに発達支援の受給者証を持っていたので、その延長で「保育所等訪問も利用したい」と伝える
・少し聞き取りを受けて、必要なところだけ記入
・30分もかからず手続き終了
そのあと
→ 役所が相談支援員さん/事業所に連絡
→ 計画書を作ってもらう
→ 受給者証が郵送で届く
という流れだった。
正直、保護者がやることは「申請に行く」くらい。
もっと大変だと思っていたから拍子抜けするくらいスムーズだった。
🧩2. 療育の先生が見てくれた“リアルな姿”
長男が支援を受け始めたのは、コロナ流行の初期のころ。
保育園と違って、小学校はとにかく中が見えない。
学級通信もなくて、先生からの電話連絡もほとんどない。
「小学校ってこんなに情報が入ってこないの?」と驚いたのを今でも覚えている。
そんな中で、療育の先生が学校を訪問してくれた。
授業1コマだけ一緒に入り、長男の様子を見て、あとで細かく教えてくれる。
連絡帳には、こんなふうに書かれていた。
・3時間目の算数の時間。机の上には1時間目の国語の道具がそのまま
・上靴がいろんなところに脱ぎ捨てられている
・プリントを提出しに先生のところへ行ったあと、そのまま友達の席に寄り道しておしゃべり
・なかなか自分の席に戻らない
・配られたプリントがそのまま机の中や床に散らばっている
その連絡帳を読んだとき、正直かたまった。
「授業、こんなふうに受けてたの?」と。
授業参観だけでは絶対に気づけない姿だった。
家では見えない「困りごと」がそこに全部出ていた。
これは長男を責めるための観察じゃなくて、
「どこでつまずいているのか」を教えてくれるメモ、という感じ。
母としても、ありがたかった。
🌸3. 先生との連携で変わったこと
保育所等訪問支援が入ってから、学校側の配慮がすごく具体的になった。
長男は「書くこと」が苦手。
黒板を写す、連絡帳に時間割を書く、宿題を書き写す…その全部が負担だった。
そこで、療育の先生が担任の先生に相談してくれて
・書く量を減らす
・オリジナルの連絡帳を用意する
という形に変わった。
今の連絡帳は、長男専用のフォーマット。
時間割を全部書き写さなくてもいいし、必要なところだけチェックすればいい。
“書くことそのもの”がハードルになっていたから、そこを下げてもらえた。
これは親だけでは提案できなかったと思う。
授業参観の30分だけ見て「じゃあこうしよう」とはならない。
実際の教室の中の様子をちゃんと見た人がいてくれたからこそ、出てきたアイデア。
学校・家庭・療育が同じ方向を向いてくれたことで、
「母だけがなんとかしようと頑張る」状態から、
「一緒に支える」に変わった感じがあった。
🌈4. 支援を受けて感じたこと
保育所等訪問支援は、名前だけ聞くと「保育所の話かな?」と思うけど、実際はぜんぜんちがう。
これは、学校生活のリアルを外から見える形にしてくれる制度だった。
・家では見えない困りごとを知れる
・学校の先生も客観的な視点をもらえる
・親も「そんなことが起きていたんだ」と知れる
・子ども自身も「責められてる」じゃなく「わかってもらえてる」に近づく
“第三の目”が入ってくれるだけで、親の肩の力が少し抜ける。
誰かが見てくれている安心感って、こんなに大きいんだと思った。
💬おわりに
「うちの子、学校でどう過ごしてるんだろう?」
「ちゃんとついていけてるのかな?」
そんな不安が頭から離れない時期だったから、
保育所等訪問支援は本当に心強かった。
授業中の姿・友達との距離感・困っている場面。
それを“記録として”伝えてもらえることで、ようやくスタート地点に立てた気がする。
もし今、同じように感じているおうちがあれば。
一度、療育の先生や自治体に相談してみるのもありだと思う。
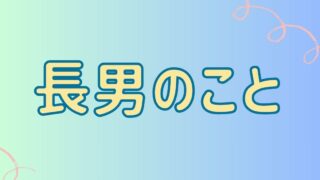

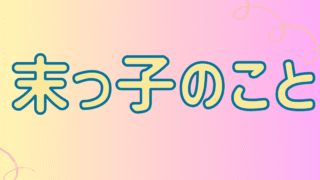

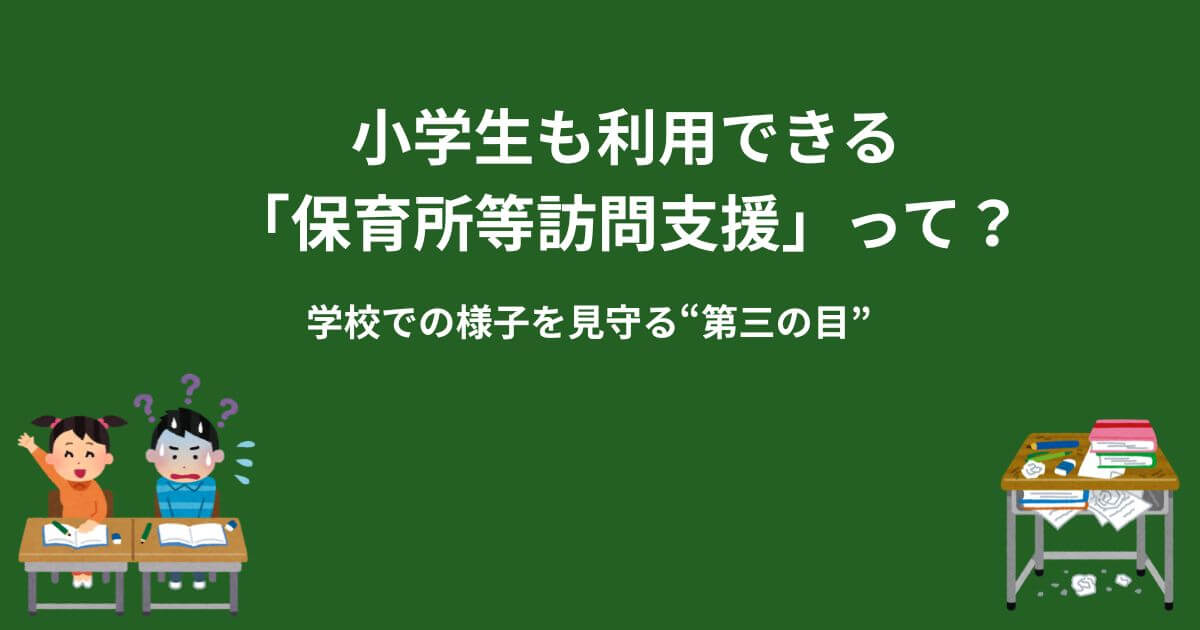


コメント