はじめに
発達障害や支援級に通う子の夏休み宿題って、普通級とはちょっと違うこともある。
うちの次男は発達がゆっくりで、まだ1年生の学習をやってるから、他の子とは進度も違う。
今回はその次男の宿題について。
普通級との違いや工夫されてるポイントをまとめてみた☺
※前回は長男の“宿題バトル編”を書いたけど、今回は次男の宿題について。兄弟でこんなに違うんや!っていうリアルをシリーズで書いてる☺
👉 長男の宿題バトル編はこちら
✏️ 先生お手製の“特製ドリル”
支援級の宿題は、市販のドリルじゃなくて先生が作ってくれたプリント集。
子どものレベルに合わせた問題がファイルにまとまってて、“オリジナル教材”みたいな感じ。
夏休み前に先生から「2年生用のドリルを買うか、次男用に用意するか」って相談があった。
無理にできない問題をやらせてもモチベ下がるし、自己肯定感も下がる気がして、先生お手製をお願いすることに。
実際にやってみたら、自信を持って解ける問題も多くて「できた!」って顔が見られたのがよかった。
配られたときは「他の子と量も質も違うし、差がまた開くんかな…」って不安もあったけど、目の前の次男は楽しそうに解いてたし、そこが大事だなって思った。
📚 宿題は“音読”と“お手伝い”
次男の宿題はドリルのほかに「音読」と「お手伝い」。
- 音読:ひらがなを“音”として読んじゃうから、単語ごとに「/」を入れて区切って読めるように工夫してる。おしゃべりはめちゃ得意やのに、文章読むとなると抵抗感があるみたい。
- お手伝い:水筒係、お箸並べ、電気をつける係。あとは末っ子のお世話。正直これが一番助かってる(笑)。
普通級の子が自由研究や感想文に追われてる中、支援級では“生活に直結する宿題”があるのが特徴的。
*ちなみに長男は、次男の宿題の少なさと簡単さにずーっと不満タラタラ💦
🤔 普通級との違いと感じたこと
「自由研究も感想文もないのいいな〜」って思う反面、「やっぱり違うんだな」って最初は戸惑いもあった。
でも実際は、その子に合った課題を通して「できた!」を積み重ねることが一番大事なんだなって思う。
長男が感想文のテーマでうなってる横で、次男は水筒を洗ったりお箸を並べたり。
一見ギャップあるけど、どっちも「自分に合った学び」でちゃんと成長してる。
🍉 まとめ 〜兄弟でちがう宿題〜
支援級の宿題ってシンプルに見えるけど、先生のお手製ドリルや生活スキルにつながるお手伝いってめちゃ意味ある宿題。
「宿題=勉強」だけじゃなくて「宿題=生活練習」って発想、これは支援級ならではの工夫だと思う。
ただ一つ問題が…。
横で自由研究に苦しんでる長男からは、毎日のようにこう言われる。
「なんで次男だけ宿題少ないん!?ズルいーー!!💦」
「ぼくはこんなにたくさん問題とかないとあかんし、種類もたくさんあるのに!」
母としては「それぞれに合った宿題だからね。学年も違うし量は差があるよ!」って説明しながら、内心ちょっと笑ってる🤣
長男が「ズルいーー!」って叫んでる横で、次男はマイペースに水筒を拭いてる…。
同じ“夏休みの宿題”でも、兄弟それぞれこんなに違う。
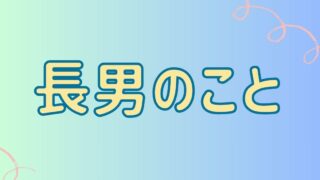

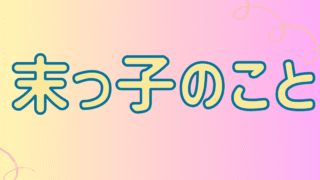

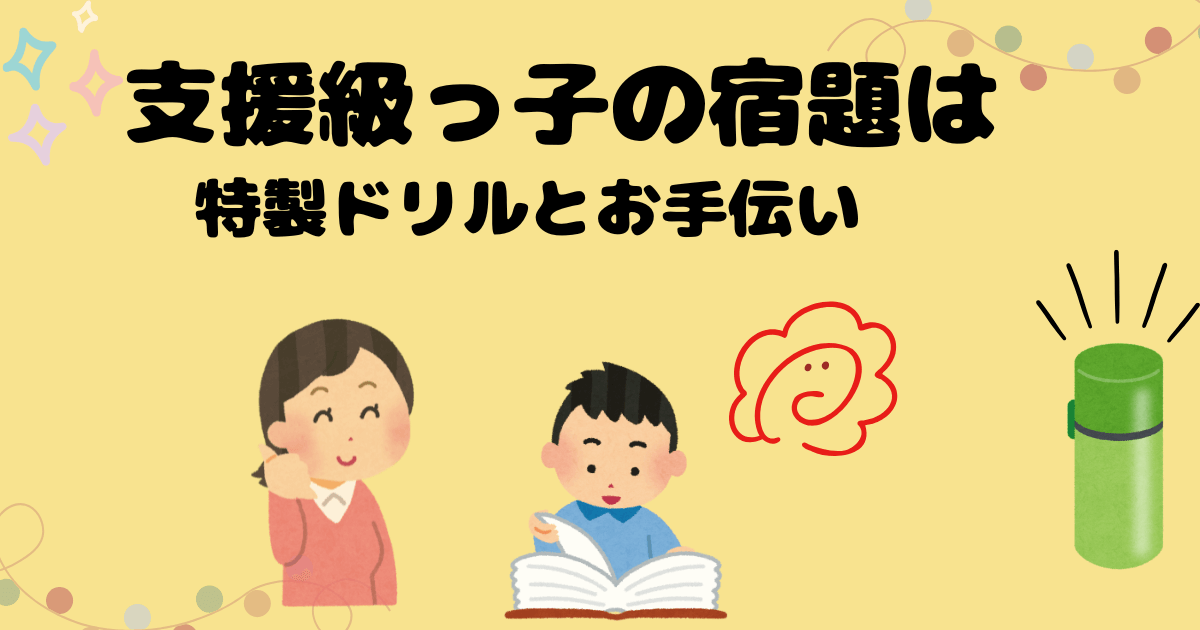
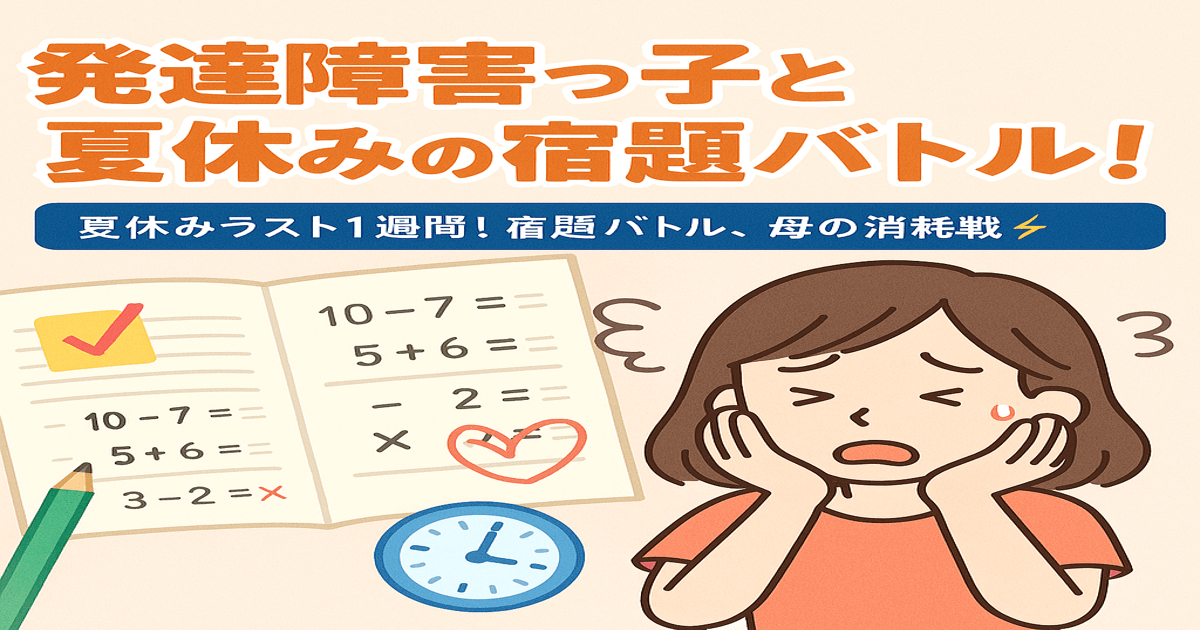
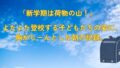
コメント