保育園の先生に相談してみたこと
年中のころ。
5歳児集団検診で少し気になると、市の発達相談室から電話があった次男。
発達相談室で再度の面談をしてもらったけれど、やっぱり「遅れがあるのではないか」とのことで、発達検査を受けることになった。
ただこの発達検査は臨床心理士の同席が必要で、できる日が限られていた。
検査の日まで少し間が空いた。その間に私なりにできることをしようと思って、まずは保育園の担任の先生に相談してみた。
先生の話によると、次男は「形」や「数」で困っていることが多いそう。
- ▲を書こうとすると、どうしても四角になる
- 無理に四角を書かせると、トゲトゲといびつな形になる
- 「∴」と点を打ってつなげるようにサポートすると、やっと▲がかける
- でも▲を見て「■やー」と言ってしまう
- 〇・☓・☆・♡はわかるけれど、▲は特に苦手
- できる日とできない日の差が大きい
- 「もの」や「数」もあいまい
その話を聞きながら、
「あぁ、やっぱり家庭だけでは気づけなかった部分があるんだ」と感じた。
家ではお絵描きをあまりしないし、したとしても比較対象は長男と次男だけ。
だから、それが遅れなのかどうかなんて、気づけなかったと思う。
家では「そのうちできるようになるのかな」と流してしまっていたことも、先生にははっきり見えていたんだと思う。
たくさんの園児を見ているからこそ、少しの違いにも気づける。
その視点に、あらためて先生への感謝の気持ちがわいてきた。
発達検査当日
そしていよいよ迎えた、初めての発達検査。
次男は少し緊張というか、「何をするんだろう」と不思議そうな顔。
でも、普段は保育園なのに自分だけお休みして両親生まれったばかりの末っ子と出かけられるのが嬉しそうな様子だった。平日なので長男は小学校へ。
前回の面談で担当してくれた先生がやさしく声をかけてくれて、安心したのか落ち着いて受けることができた。
検査は臨床心理士の先生と次男の二人きり。私たちは別室で待機。
その間、担当の発達相談室の保育士さんと、保育園で聞いてきた内容を伝えたりしていた。
夫は末っ子を抱っこしながら、静かに時間が過ぎるのを一緒に待ってくれていた。
1時間ほどして、臨床心理士さんと次男が戻ってきた。
検査結果は1ヶ月後とのことで、次の予約を決めてその日は終了。
「おつかれさま」と声をかけると、次男は
「めっちゃたいへんなんやから。あぁ疲れた」
と一言。
その姿に「よくがんばったな」と労いながらも、
「どんな結果が出るんだろう」
「もしできなかったら?」
そんな思いが頭から離れなくて、待っている間ずっと落ち着かなかった。
帰り道、コンビニに寄って、シュークリームを買った。
帰宅の車内でたくさんで1時間もよく頑張った保育園児の次男をたくさん褒めた。
次回へ
こうして、次男にとって初めての発達検査は無事に終わった。
けれども、結果が出るまでの1ヶ月は長くて長くて…。
「どうか、これからの見通しが立ちますように」
そんな気持ちで過ごした結果については、次回に書こうと思う。
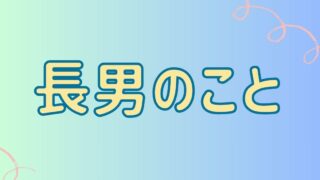

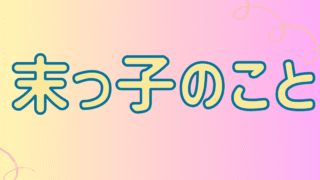

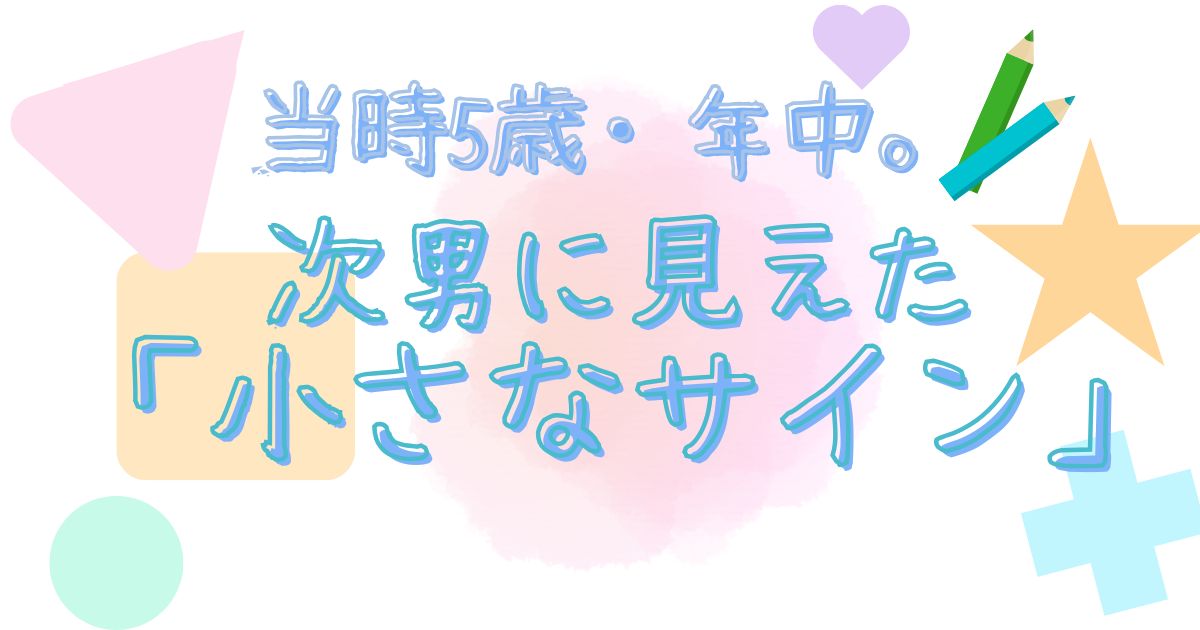
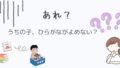

コメント