「うちの子、ちょっと発達ゆっくりかも?」
そう思ったのは、次男が年中の終わりごろ。人懐っこくておしゃべりも達者だから気づかなかったけど、ふとした瞬間に「あれ、ひらがな読めない?」って違和感があった。
保育園に相談しても“その子によりますよ”で片づけられてモヤモヤ…。
そんなとき、市からの電話でまさかの展開に。
今回は、次男が初めて発達検査を受けることになったきっかけを振り返ります。
きっかけは「ひらがなが読めない?」
今、小2の次男。診断名はついてないけど、いわゆる“発達グレーゾーン”。
人懐っこくてよくしゃべるから、最初は全然気づかなかった。
でも年中の終わりくらいから、「あれ?ひらがな、全然読めないぞ?」って気になり始めた。
そろそろ自分の名前くらいは読める年齢なのに、読もうとする気配なし。
長男はこのころ、外食のメニューから自分の名前を探して遊んでた。どうしても比べちゃう…。
保育園に相談してみたけど…
主任の先生と担任にちらっと相談してみた。
そしたら返ってきたのは、
「その子によりますよ。気になるならお母さんが本をいっぱい読んであげてください」
……え、そういう感じ?
ただ「遅れてる?」って聞いただけなのに、「家庭でなんとかして」って突き返された気がして、なんかモヤモヤ。
半年後、市からの突然の電話
そのまま半年くらい経ったころ、市の発達相談室から電話があった。
「次男くんのことなんですけど。先日の集団健診で様子を見せてもらって…。もう一度ゆっくり見せてほしい」
最初は長男のことかと思ったら、まさかの次男。
実は年中で受けた市の集団健診で“発達の遅れ”を指摘されてたらしい。
新しく始まった「5歳児健診」
調べてみると、これは新しく始まった 「5歳児健診」 の一環。
こども家庭庁が主導して2024年度から全国で本格的にスタートした制度で、発達の特性を早めに見つけて支援につなげるのが目的。
長男のときにはなかった制度。ちょうど次男が対象だった。
面談の日。お絵かきがまさかのテスト
後日、市の保育士さんと臨床心理士さんと面談。
私はこれまでの様子を話し、その横で次男はお絵かき。
でもこれ、ただのお絵かきじゃなかった。実は形や数の認識をみるテスト。
出てきた結果と気づき
お絵かきの後、伝えられたのはこんなこと。
- 四角や三角、十字がうまく描けない
- 3以上の数がまだ分かってない
- 鉛筆を持つ手に力が入らない
- 手先が不器用
- おしゃべり止まらない
- 発音がちょっとあやしい
- 1つのことに集中しづらい
- 分からないとふざけちゃう、助けを求められない
この結果を受けて、「ちゃんとした発達検査を受けましょう」ってことになった。
まとめ:違和感+制度のタイミングでつながった支援
次男が発達検査を受けることになったのは、私のちょっとした違和感と、新しく始まった5歳児健診が重なったから。
勇気出して相談してもスルーされることもあるけど、制度に助けられて専門につながることもあるんだなと実感した。
次回予告|発達検査当日の様子と保育園での再聞き取り
次回は、いよいよ 発達検査当日のリアルと、保育園での“再聞き取り” の話を書こうと思う。
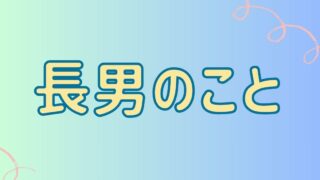

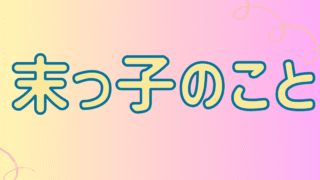

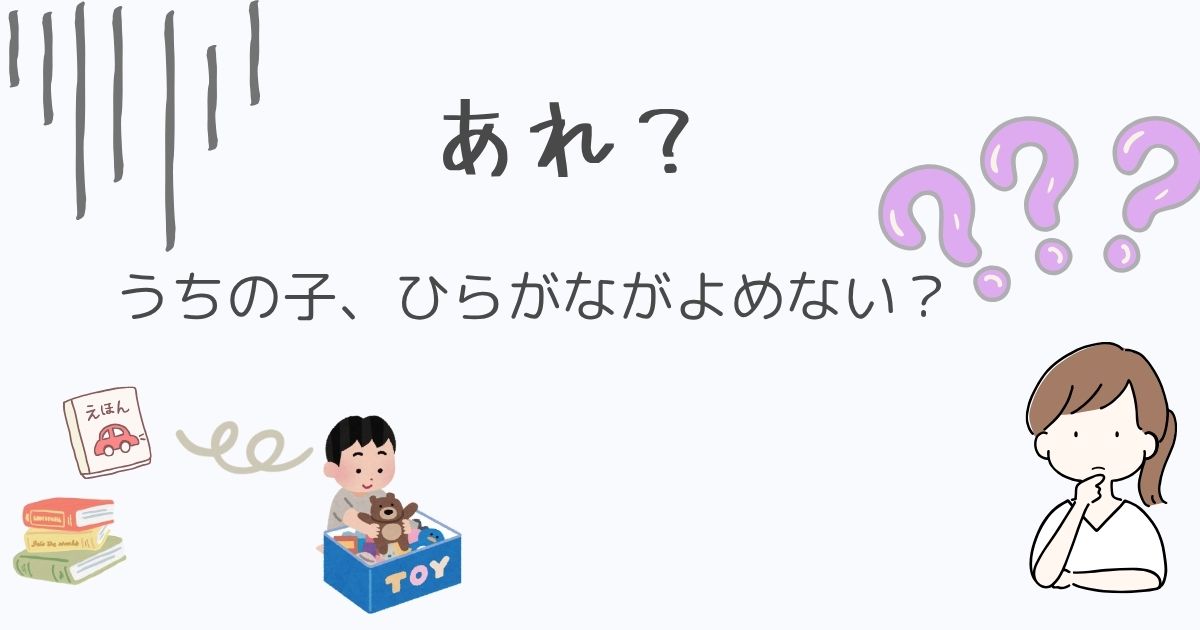
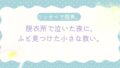

コメント