検査結果を聞く日は、やっぱりドキドキ。
今回の新版K式発達検査では「1年3か月の遅れ」という結果が出ました。
数字だけを見ると不安になるけど、生活に密着した得意もしっかり見えてきた。
先生や保健師さんからのアドバイスと、家庭でできる工夫をまとめます。
新版K式発達検査を受けて
(5歳2か月で実施)
検査結果を聞く日。
この日は夫が出張で、親は私ひとり。
生まれたばかりの末っ子を抱えながら、臨床心理士の先生から検査の話を聞いた。
まずは検査結果の紙を受け取り、結果の見方や補足を丁寧に説明してもらう。
ドキドキしながら聞いた内容を、ここに残しておこうと思う。
発達年齢と発達指数(DQ)って?
検査では「発達年齢」と「発達指数(DQ)」という2つの指標が出る。
- 発達年齢:その分野でどのくらいの年齢相当か
- DQ(発達指数):実年齢に対する割合(100が同年齢相当)
次男(実年齢5歳2か月)の結果はこんな感じ。
- 認知・適応:3歳7か月(DQ 69)
- 言語・社会:4歳2か月(DQ 81)
- 全領域合計:3歳11か月(DQ 76)
※姿勢・運動の分野もあるけど、次男ははできていたので、今回は記載なし。
実年齢と比べると1年3か月の遅れがあり、成長はゆっくり。
ただ、生活に密着したことについては年齢以上の回答もできており、得意な部分も見られた。
指摘されたこと
先生からは、具体的にこんなことを教えてもらった。
- 数はかぞえられるけど、意味は理解できていない
- 「多い・少ない」がまだわからない
- 聞いて覚えることが苦手
- 自分で数えるのが難しく、このままでは字を覚えるのも苦手になりやすい
- 正方形を描くと角が丸くなってしまう
- 形を覚えるのが苦手
- 応用したり考えたりする課題が苦手
また、自分で「できない」と思った問題に対して取り組みにくい様子もあり、少し自信を失っているように見えた。
だからこそ、褒めるときは結果だけじゃなく、経過を褒めることが大切。
本人に合わせた問題を取り組ませ、達成感を持たせてあげることが良いと言われた。
家庭でできる工夫
じゃあ、どう関わっていけばいいのか。
先生が教えてくれた具体的な方法はこんな感じ。
- 体をいろいろ動かす遊び
→ サーキット遊びなど - 数字を交えたお手伝い
→ 「〜と〜を3つ持ってきて」と伝える - 指先を使う作業
→ ミニトマトのヘタを取る/レタスをちぎる - ブロック・レゴ遊び
→ 手先を使って工夫する力を養う - 工作あそび
→ 線をマジックで引いて、それを切ってもらう - 遊びながら学ぶ
→ 迷路、写し絵、点つなぎ
遊びや生活の中に自然に取り入れていくのがポイントとのこと。
今後の方向性について
検査のあとは、市の保健師さんから今後の方向性についても説明を受けた。
療育の利用や家庭での関わりを続けることに加えて、運動機能についてもアドバイスがあった。
長男のときに「体幹を鍛えるのに水泳がいい」と勧められ、次男も一緒に始めていた。
今回も「そのまま水泳を継続すると良い」と言ってもらえた。
次男にとっても楽しみながら体を動かせる大事な活動になりそう。
同じように不安を感じている親御さんへ
発達検査の結果って、どうしても数字に目がいきがち。
私も「1年3か月の遅れ」という言葉に心がざわついた。
でも、先生や保健師さんの言葉を聞いて「できることを大事にすればいい」と思えるようになった。
もし今、子どもの成長に不安を感じている人がいたら、
どうか数字だけで判断せず、その子の得意や小さな成長に目を向けてみてほしい。
まとめ
数字だけ見ると正直落ち込む部分もある。
でも先生から遊びやお手伝いを通して、少しずつ積み重ねていけば大丈夫
と声をかけてもらい、気持ちが少し軽くなった。
さらに「経過を褒めること」「本人に合った課題で達成感を持たせること」が大切だと教わり、ハッとした。
普段それがちゃんとできていたかな…と少し不安にもなったけど、これからはもっと意識して関わっていこうと思った。
そして保健師さんからも「水泳を続けて体幹を鍛えるのは良い」と言われ、これまでやってきたことが次男の力につながるんだと実感。
「できない」に注目しすぎず、「できること」を伸ばす。
次男のペースで、日常の中で楽しく関わりながら成長を見守っていこうと思う。
次回予告
検査結果をふまえて、このあと具体的に「療育」や「支援級」の話が出てきた。
次の記事では、先生や保健師さんから聞いたその内容と、私が感じた正直な気持ちを書いていく。
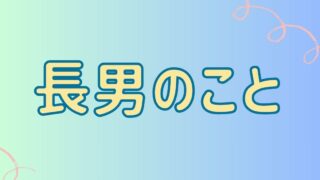

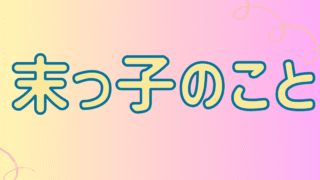

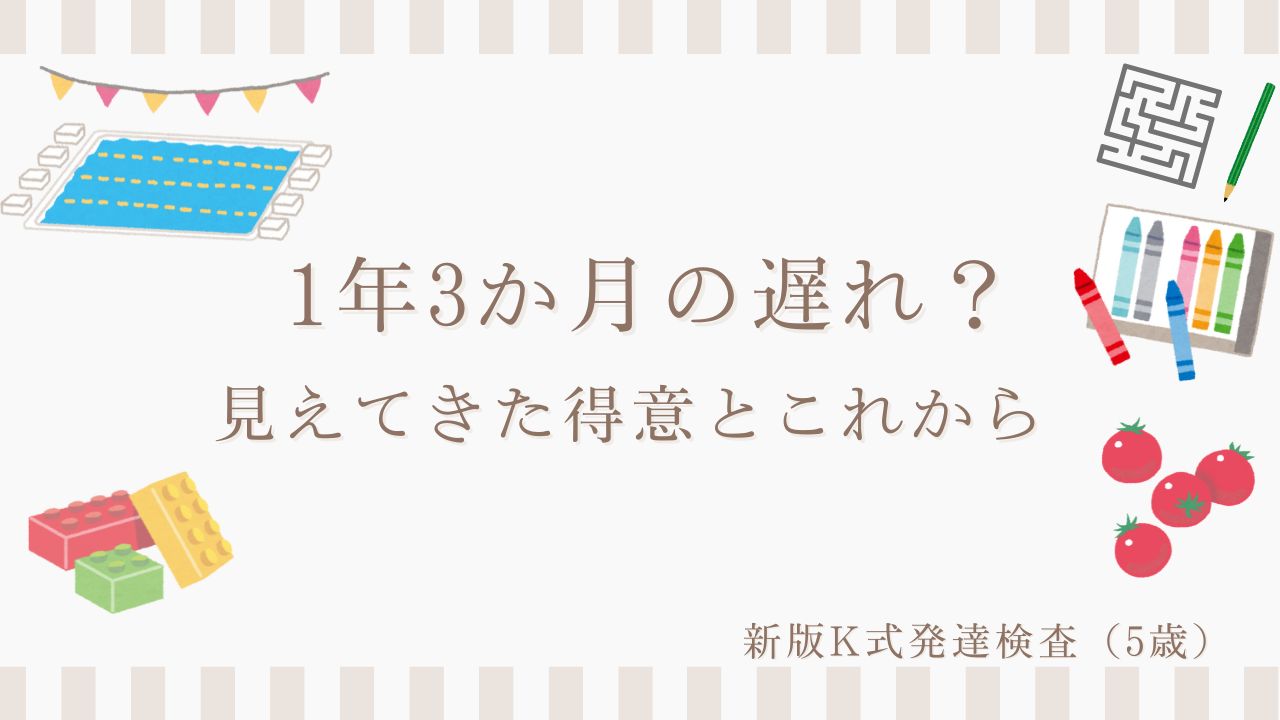


コメント