小学校に入ってから、長男の様子が少しずつ変わっていった。
保育園では特に問題もなく過ごしていたのに、学校では行きしぶりや涙の場面が増えていった。
あのときは理由もわからず、ただ心配でいっぱいだった。
今回は、そんな長男が療育を始めるまでの流れと、通い続ける中で見えてきた変化のことをまとめてみようと思う。
🕊️小1の冬、はじめて見えた“違和感”
小1のころ、長男に行きしぶりが始まった。
ちょうどコロナの感染が広がりはじめた時期で、学校での様子がほとんどわからないまま日々が過ぎていた。
そんなある日、学童から電話があった。
「長男くんが“自分なんて…”と言いながら泣き出して、壁に頭を打ちつけてしまって…」
その話を聞いたとき、ただ驚いて頭の中が真っ白になった。
保育園では特に問題を指摘されたことはなかった。
でも、どうやら小学校では授業がうまく受けられていないらしい。
そこから周囲の先生方にも聞き取りをしていくうちに、少しずつ現実が見えてきた。
そして、発達の凸凹が影響しているかもしれないと考え、発達検査を受けることにした。
結果、言語理解が高い一方で処理速度やワーキングメモリが低く、苦手な場面での困りごとが多いことがわかった。
🌱療育スタート。見守られながらの第一歩
放課後デイサービス(療育)を始めたのは、その結果を受けてから。
ちょうど、もともと通っていた学童が療育支援を取り入れ始めたタイミングでもあった。
「環境が大きく変わるのでは?」という不安もあったけれど、
顔なじみの先生やスタッフが近くにいたことで、本人も抵抗なく通い始められた。
人と関わるのが好きなタイプなので、人見知りはまったくなし。
母としても、信頼できる先生方(園長先生や理事長)が見守ってくださる安心感が大きかった。
ちなみに、療育を担当してくれる先生と学童スタッフの先生は別の方。
それでも、しっかりと連携を取ってくださっているのが伝わってきた。
🌈通い続けて見えた変化
あれから数年。
今は、安定した日常を過ごせている。
一番の変化は、「困ったときの相談先ができたこと」。
家庭の中だけで抱えこむのではなく、専門的な視点からアプローチしてもらえるのは本当に大きい。
物の管理の仕方や怒りのコントロール、友達との関係の持ち方──
どれも家庭だけでは教えきれなかった部分を、第三者の視点でサポートしてもらっている。
ときには先生から「学校ではこう見えている」「家庭ではこう感じている」とすり合わせをしてもらえることで、親の見方も広がった。
何より、彼自身が“安心して頼れる人”を見つけられたこと。
それが、あの頃の「自分なんて…」という言葉を少しずつ手放していくきっかけになった気がする。
🌸同じように悩んでいるお母さんへ
行きしぶりや泣いてしまう日があっても、それは“困っているサイン”。
療育を始めたことで、私は「親も支えてもらっていいんだ」と感じました。
お子さんの「何が」「どのように困っているのか」、そして「どうすればサポートしてあげられるのか」を、
少しでも見つけるヒントになれば幸いです。
もし迷っている方がいたら、まずは誰かに相談してみてほしいです。
次回は、学校での様子を支えてくれた「保育所等訪問支援」について書いてみようと思います。
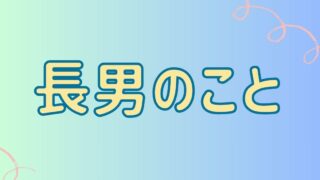

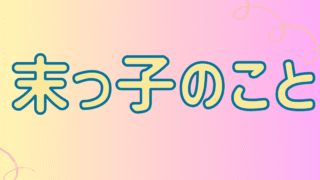

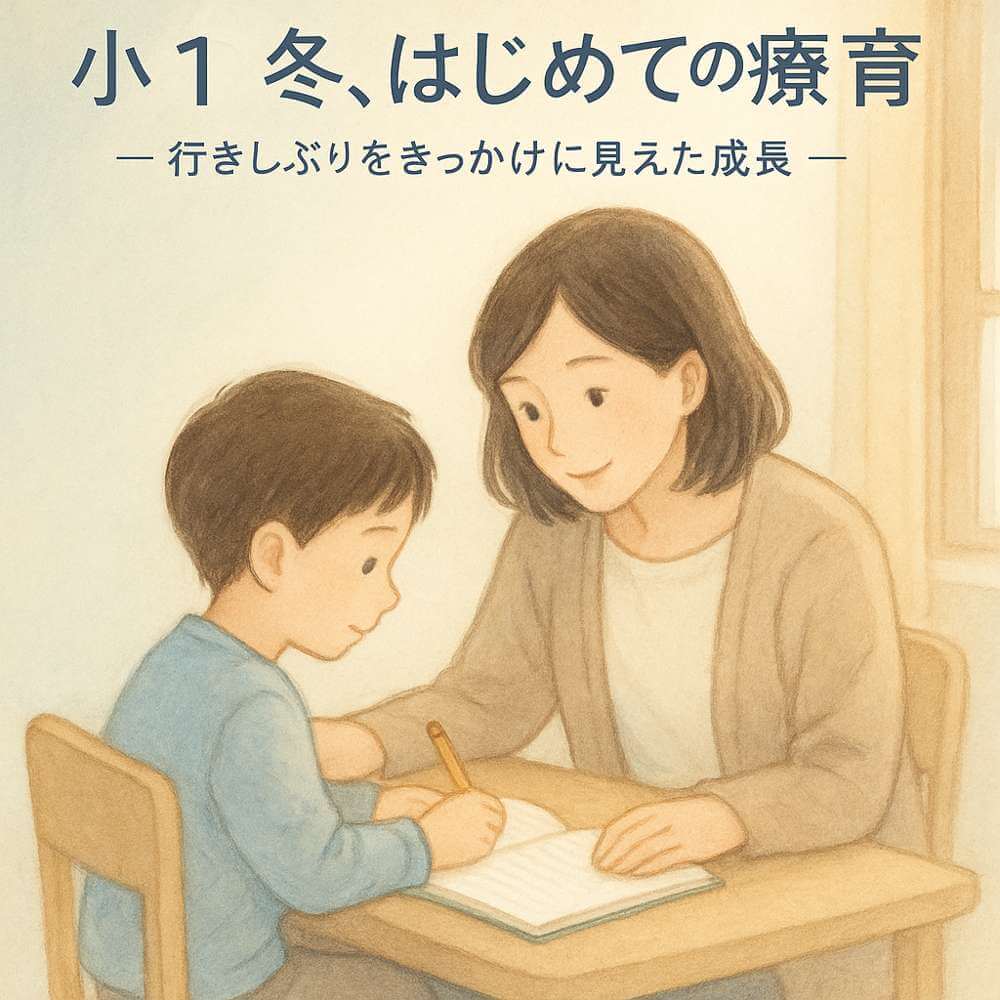


コメント