😕小学生になっても続く癇癪
次男は小学生になっても癇癪を起こすことがある。
泣き方は赤ちゃんみたいに大声で「うえーーん!」って叫ぶし、洗濯機と壁のすき間に入り込んでしくしく泣いてたり。
「反抗期かな?」って思ったけど、ただ怒ってるって感じじゃなくて、感情の切り替えができなくてパニックになってるんやな、って最近は思う。
😢癇癪が起きたときの様子
ある日も、ちょっとしたきっかけで大泣き。
思い通りにならないと、机の上のものをひっくり返したり、私にパンチしてきたり…。
体が大きくなってきてる分、こっちも対応にめっちゃ体力いる。
「もうどうしたらいいんやろ」ってなることもある。
こっちもつられて感情たかぶることもある。だから、冷静にならないとって自分に言い聞かせる⋯。
🤱母が試した対応
癇癪に振り回される毎日だけど、いろいろ試してみたこともある。
💬声かけを最小限にした
なだめようとして長く話すと、逆効果になることが多かった。
しつこく声掛けしすぎても本人の感情を逆なでしてしまったことが多々のあったから、少し間を開けるようにした。
🛏️安心できる隠れ場所を許した
洗濯機のすき間とか布団の中に隠れることもある。
前は「出てきなさい!」って言ってたけど、今は「落ち着くまではまあいっか」って考えるようになった。
⏳落ち着いてから振り返る
癇癪中に話しても通じない。
でも、たまにちらっと顔を出して、電気つけたり別の部屋でエアコンついてないところに隠れたらエアコンつけたりして声はかけないけど「大丈夫」「ここにいるよ」「気にかけているよ」って態度で伝えるようにしてる。
本人の感情が落ち着いて自分から出てきたときに 後で「どんな気持ちやった?」「どうしたらよかった?」って振り返るようにしてる。
本人も私も感情がクールダウンできて冷静に話し合える。
🔍癇癪と反抗期の違い
次男の様子を見てると「これは反抗期とはちょっと違うな」って思う。
反抗期は「イヤ!」とか「自分でやる!」みたいに主張することが多いけど、次男の場合は「気持ちが処理できなくてパニックになる」感じ。
癇癪って、困ってるサインなのかもしれない。
🌿まとめ:母が学んだこと
今回のことで思ったのは、癇癪を無理に止めるより「安全を確保して待つ」ほうが落ち着きやすいってこと。
そして何より母が落ち着いてるほうが、子どもも安心するなぁって。
発達グレーの子どもたちと向き合う中で、感情の波に振り回されることって本当に多い。
イライラしたり、泣いたり、爆発したり…そのたびに「私の関わり方が悪いのかな」って落ち込むこともある。
母だって人間。いつも余裕があるわけじゃない。
時間に追われてたり、家事や他の子の世話で手いっぱいなこともあるし、ホルモンバランスのせいで感情コントロールが難しいときだってある。
つい対応を間違えて、余計にこじらせちゃうことも正直たくさんある。
でも、試行錯誤していく中で気づいたことがある。
「うまくいかない日があっても大丈夫」
「お母さんが笑顔でいられることが一番」
この2つ。
完璧に乗り対応する必要なんてなくて、感情の波に飲み込まれそうなときは「今日はもう休もう。一旦休戦!」くらいの気持ちでいいんだと思う。
そして、癇癪が落ち着いた後に「さっきはどうしたかった?」って聞いてみると、意外とシンプルな答えが返ってくることもある。
「ママに見てほしかった」とか「一人でやりたかった」とか。
そういう小さな気づきが、次の対応のヒントになる。
きょうだいたちも、最初は戸惑って泣き声にイライラしていたけど、少しずつ慣れたというか、他の子達も次男をそっとしておいてくれている気がする。
家族みんなで少しずつ成長してるんやなって思う。
同じように悩んでる人に、「一人じゃないよ」って伝わったら嬉しい。
感情の波はなくせないけど、寄り添いながら少しずつ進んでいけたらいいなって考えるようになった。
「癇癪=困ってるサイン」って受け止めて、これからも関わり方を探していこうと思う。
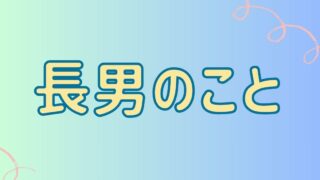

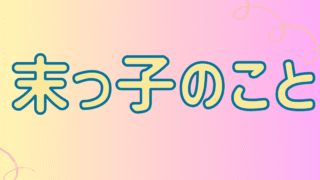

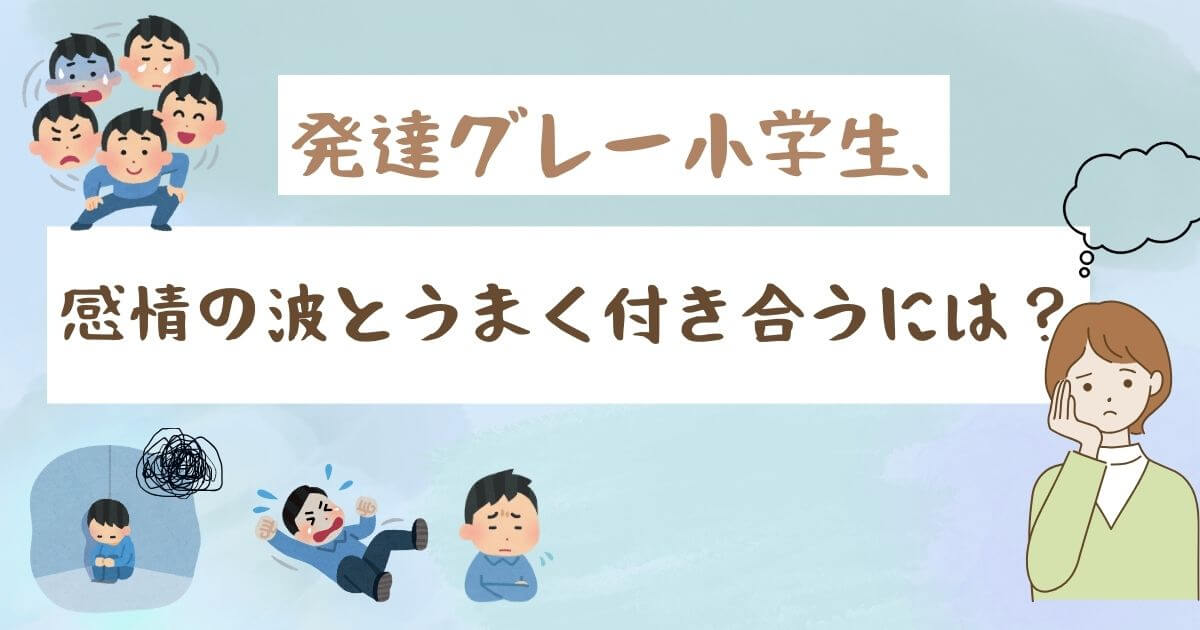

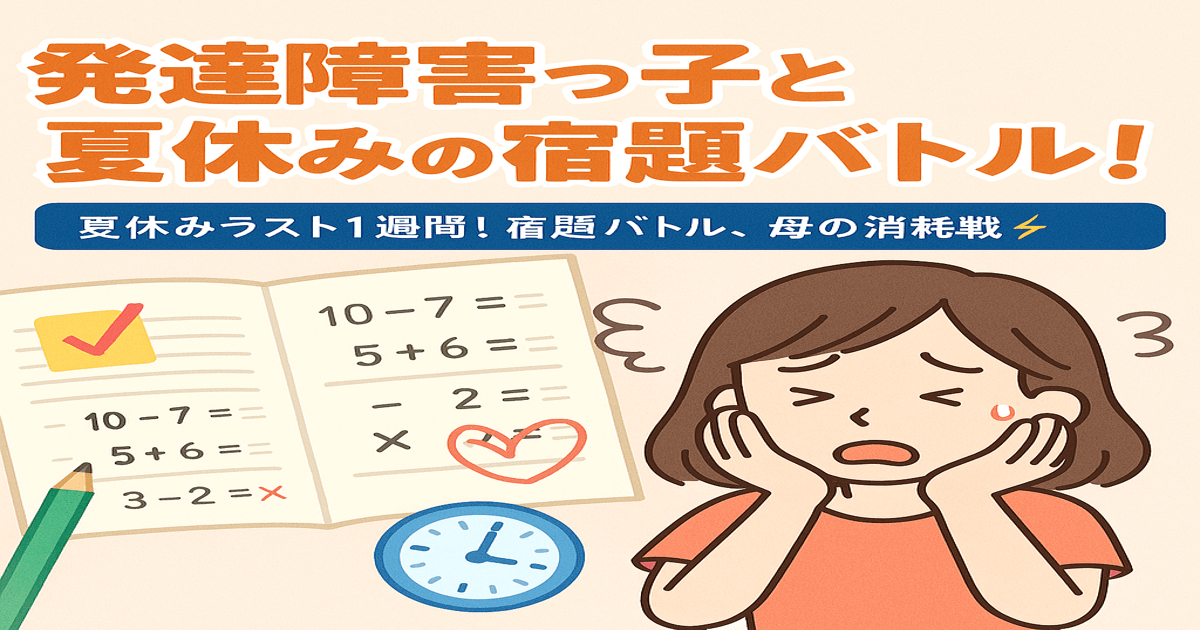
コメント