うちの次男は、保育園の頃に発達の遅れを指摘されて、そこからずっと療育に通っている。
初めての発達検査のとき、保健師さんと臨床心理士さんから
「一般的に“発達グレー”と言われている、まさにそのグレーゾーンです」
そう聞いたときはびっくりして、正直どう受け止めていいかわからなかった。
小学校では1年生から支援級に在籍。
初めての発達検査から約3年たった今も、次男との関わり方はまだまだ模索中。
そんな中で出会った『マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち』は、
まさに“うちの子のことだ”と思う場面の連続だった。
専門用語が少なく、マンガで描かれているからスッと心に入ってくる。
発達が気になる子だけじゃなく、診断のある子や定型発達の子にも通じる
“感じ方のちがい”がとてもわかりやすく描かれている。
読みやすくて、心に残る一冊
最近読んだ中で、すごく心に残った本。
うちの次男はまさに“グレーゾーン”の子で、
読みながら何度も「これ、うちの子だ…」「こんなこともあったな」と胸がチクッとした。
この本はマンガで描かれていて、専門用語も少なくてとても読みやすい。
文字だけじゃ伝わりにくい“子どもの気持ち”や“空気のズレ”が、
絵の表情や仕草からスッと入ってくる。
「なるほど、こう感じてたんだな」と、納得した。
漫画で読みやすいし、祖父母や長男にも読んでもらって
少しでも次男への対応のヒントになればと思っている。
自信をなくす子どもの姿に重なる思い
特に心に残ったのは、「自信をなくしていく子ども」の姿。
できないことを繰り返し指摘されるうちに、
「また怒られる」「どうせ自分はダメなんだ」と思い込んでしまう流れが、まさにうちの次男そのものだった。
頭ではわかってる。
“できてないところ”よりも、“できてるところ”を見つけよう。
“間違い”よりも、“挑戦しようとした気持ち”を大事にしよう。
そう思っているのに、日常の中でつい口が出てしまう。
音読の時間で気づいた「やる気の壊れやすさ」
この本を読んで2日後くらいに、まさにその「失敗」をした。
次男が音読の宿題をしていた。
その日は珍しく自分から「今日はちゃんと読むね!」とやる気を見せてくれて、
わたしも「お、いい感じ!」と思いながら横で聞いていた。
でも、途中から気になってしまった。
語尾を勝手に変えたり、漢字を飛ばしたり。
つい、「〇〇でした → 〇〇であった、だよ」とか、「今の読み飛ばしたよ」と言ってしまった。
言った瞬間に、空気がピシッと変わった。
次男の顔が少しこわばって、目線が床に落ちた。
「もう!いちいち言ってこんといて!」
そのまま本をパタンと閉じて、ソファに顔をうずめた。
一瞬で、せっかくのやる気が消えていった。
「本読みをがんばってるのに、わたしが削いじゃった…」
その後ろ姿を見ながら、胸の奥がギュッとなった。
気づきと反省
思えば、あの時の私は「正しく読ませる」ことに意識がいってた。
「丁寧に読む練習になる」「間違いを直してあげた方がいい」と思い込んでた。
でも、次男にとっては“せっかく頑張ってるのに注意ばかりされる時間”になっていた。
できなかった部分を指摘されるたびに、
「また怒られた」「もうやりたくない」って気持ちが積み重なっていたのかもしれない。
そして気づいた。
“やる気”って、すごくこわれやすい。
ほめられると一気に広がるけど、
小さな一言で、あっという間にしぼんでしまう。
大人のわたしでも、仕事で指摘ばかりされたら自信なくす。
ごめんよ、厳しい上司みたいなことしてしまって…って反省。
見守る勇気
次の日、音読の宿題の時間。
私はいつもみたいに横にはつかず、台所からそっと聞くだけにした。
読めなくても、間違っても、何も言わない。
次男は最初、こちらをチラッと見たけど、
そのまま最後まで読み切った。
終わったあと、照れくさそうに「終わったよ」と一言。
「最後まで読めたね」
ただそれだけ言ったら、
「うん」と少し笑って、教科書を閉じた。
たぶん、あの一言で十分だったんだと思う。
“できた”をちゃんと見てもらえること。
それが、彼にとって何よりのごほうび。
正直、音読だから正しく読めるようにサポートしたほうがいいのかなとも思う。
でも今は、彼の自信ややる気を認めるほうがずっと大事だと感じている。
グレーゾーンだけじゃない、誰にでもある姿
この本は「境界知能」「グレーゾーン」と書かれているけど、
読んでみると、診断のある子にも共通する部分がたくさんある。
うちの長男にも「あ、ここ似てる」と思うところがいくつもあった。(長男はADHD)
そして思った。
一般的な“定型発達”の子でも、
「これって誰にでもあるんじゃない?」と感じる部分がけっこう多い。
ただ、同じ状況でも、
発達に凸凹がある子は“どんなふうに受け取って”“どう反応するか”が少し違う。
その違いを、マンガでわかりやすく描いてくれている。
だから、「うちの子はグレーかも?」と思う人だけじゃなく、
子どもの“感じ方の多様さ”を知りたい人にもおすすめ。
発達のことって、言葉で説明されるより、
「その場面でどう見えるか」「どう感じているか」がわかると一気に理解が深まる。
この本はまさに、そこが伝わる一冊だった。
子どもと一緒に育つということ
子どもを理解しようとすること。
自分の関わり方を見つめ直すこと。
その両方が、親としていちばん大事なスタートライン。
完璧じゃなくていい。
失敗して、気づいて、少しずつ優しくなっていけたら、それでいい。
この本は、そんな気づきをくれる一冊だった。
まとめ
- 「できない」より「やってみようとした」気持ちを見てあげる
- 間違いを指摘するより、最後までやり切ったことを認める
- 親も“正しさ”より“安心感”を届けることを意識する
発達が気になる子にも、定型発達の子にも。
子どもの“心の中の見え方”を知りたいすべての人に読んでほしい。
ちなみに、次男のいいところは日常の中にたくさん散らばっている。
料理をしたり、小さい子の面倒を見たり。
やさしさも思いやりも、ちゃんと育ってる。
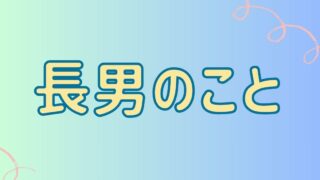

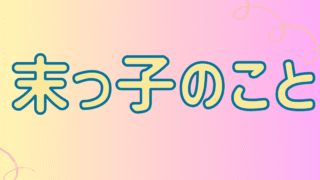




コメント