保育園児が療育に通う1日の流れ
「保育園に通いながら療育も利用するって、どんなスケジュールになるの?」
うちの次男が保育園児のときは、週3回(月・水・金)の午後に療育があった。
三時のおやつを食べてから、療育の先生が保育園まで迎えに来てくれて、1時間の活動。
終わったあとはまた保育園に送り届けてもらえるシステムだったから、親としてはすごく助かった。
今日は、そんな保育園児が療育に通っていた頃のリアルな1日を紹介。
📝療育に通う日の流れ(保育園ver)
7:30〜9:00 保育園登園
9:00〜15:00 保育園で過ごす(給食・お昼寝・遊び)
15:00 三時のおやつ
15:30〜16:30 療育(先生が保育園まで迎えに来てくれる)
16:30過ぎ 療育後に保育園へ戻る
17:00〜18:00 母が保育園へお迎え(仕事終わりに直行)
18:00〜21:00 帰宅・夕飯・お風呂・寝かしつけ
🚌 保育園と療育の行き来
次男が通っていた療育は、保育園児専用の枠があって、先生が直接保育園まで迎えに来てくれるスタイル。
活動が終わったらまた保育園まで送ってくれるので、親の送迎は不要。
この仕組みが本当にありがたくて、私も仕事をしていたから「療育のたびに車で送り迎えする」負担がなかったのは大きかった。
送迎の心配をしなくていいのは、共働き家庭や下の子がいる家庭にとって大助かりだと思う。
🍪 おやつのあとにスイッチ切り替え
療育が始まるのは15:30。ちょうど三時のおやつを食べたあと。
友だちと遊び始めたタイミングで療育のお迎えがあったりしてシュンとする時やお友達と遊んでテンションが高いまま行く日もあった。
「眠いのにがんばれるかな?」と心配した日もあったけど、先生が歌や体を使った遊びを取り入れてくれたり、お部屋に当時彼が好きだったウルトラマンのイラストを壁に貼ってくれたり嫌にならないように彼ができることを多めに取り入れながら、後半に少し次男の苦手を入れるという作業にしてれてた。
保育園のリズムと療育の活動がうまくつながっているのを感じて、安心して任せられた。
保育園も年中、年長になってくると行事ごとでたくさんの練習をしないといけない。
運動会で太鼓の練習や、生活発表会のときには劇の練習など…
本番近くなってきてクラスでの練習とか保育園全体で通し練習の時とか、保育園のイベント事が近い時とかは療育はお休みしてた。
あとは保育園の担任の先生がクッキングや製作、ドッジボール大会など企画してくれた日も
療育はお休み。
小学生になると離れてしまう友だちもいるし、保育園では保育園の思い出をたくさん作ってほしかったから
思い切って療育をお休みするようにしてた。
🏃♀️ 親の仕事とお迎え事情
私は仕事が終わったら、そのまま保育園へ直行。
療育から帰ってきた次男を17時ごろに迎えに行くのがルーティンだった。
「今日は疲れてるかな?」「眠くてぐずらないかな?」と考えながら向かうのは、ちょっとドキドキ。
療育の帰りはテンションが上がって元気な日もあれば、もう力尽きてカバンを持つのも嫌がる日もあった。
「今日は僕めちゃくちゃ頑張ったからもうむり。お母さんがかばん持って」とかいって保育園からの帰り道彼は何も持たずに私に荷物渡してくる w
帰りの車で「今日の療育どうだった?」と聞いても、疲れて眠すぎて無言…なんてことも…。
家着いたら彼はいつの間にか寝てることもしばしば。
📩 家に帰ってからの夜の流れ
夕方の療育でパワーを使い果たしているから、帰宅後はとにかく眠そう。
ごはんを食べながらウトウトしたり、お風呂でぼーっとしたり…。
でも、そんな姿を見て「今日も1日よくがんばったな」って思えた。
寝かしつけは意外とスムーズで、布団に入ったらすぐ夢の中。
おかげで夜は早く落ち着くことが多かったのは、保育園児ならではのメリットかもしれない。
✨まとめ
保育園児が療育に通うときは、送迎を先生にお任せできるかどうかが大きなポイント。
うちの場合は保育園⇔療育の送迎を全部してもらえたから、親としては負担が少なかった。
ただ、おやつのあとの眠たい時間に活動するのは子どもにとってチャレンジ。
ぐずぐずの日もあったし、疲れすぎて帰宅後に何もできないこともあった。
それでも「週3回の療育」は次男にとって大切な時間になったと思う。
生活リズムの中に療育が自然に組み込まれていたからこそ、無理なく続けられたんだと思う。
今回は保育園児の療育1日パターンを紹介したけど、
小学生の療育とは全然違う大変さやメリットがある。
ぜひ小学生編の記事と合わせて読んでもらえたらうれしい!
📌 関連記事
👉 小学生×療育 放課後スケジュール
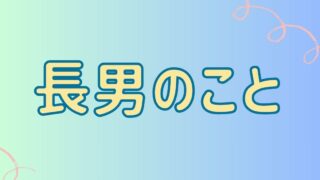

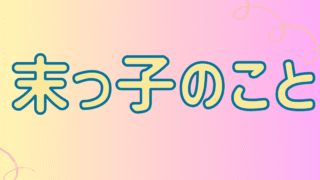



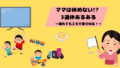
コメント