支援級での懇談に行ってきました。
プリントの工夫、座学中の体の動かし方、時間管理の支援——どれも「できる方法を一緒に探す」先生たちの姿勢に、ただただ感謝。
そして最後に夫が放った一言が、私の中にあった“思い込み”に気づかせてくれた時間でもありました。
支援級での懇談|“今”を見て、“これから”を考えるきっかけに
個別懇談ウィーク、今回は次男の支援級での懇談。
交流級(普通級)の懇談では、落ち着きのなさや友だち関係の話がメインでしたが、支援級ではもう少し本人の“特性”に向き合う話が中心になります。
支援級所属だけど、普通級でもがんばってる
入学したての頃は、支援級所属とはいえ、ひらがな・カタカナ・数字の学習スタートはみんな一緒。
だから算数や国語も、これまでは普通級で受けてきました。とはいえ、支援級の先生が普通級に入ってサポートしてくれていて、実質マンツーマンのような形。
プリントは量が半分だったり、なぞり線が入っていたりと手厚くサポートしてもらっていたようです。
時々は支援級でもうひとりの子と2人だけの授業もあり、場所や人数を変えながら、うまく組み合わせてくれているとのことでした。
クラスでの様子と、ちいさな課題たち
同じ支援級には同性の子がもう一人。よくケンカしてるけれど、それでもお互いに助け合っているところもあるみたいです。
6年生のお兄ちゃんにも甘えていて、安心できる関係の中で過ごせているのが伝わってきました。
学習面では、「6」と「9」の判別が難しかったり、ひらがなの形や大きさが安定しない。
でも、マス目にガイドとなる円を書いてあげると書きやすいことがわかってきて、それも先生たちが工夫してくれています。
集中力もまだ課題があって、周囲の音や刺激で気が散りやすいところも。
鍵盤ハーモニカは苦手で、片手1本指で演奏しようとしたり…
間違いを指摘されるとプイッとそっぽを向いてしまう。
言いすぎちゃう、止まれない
友達には少し言いすぎてしまうことがあるようです。
自分もできていないのに、相手にしつこく注意をしてしまう。
**「人への指摘がやめられない」「自分ができていないことに気づけない」**というのが、今の課題だと先生は話してくれました。
でもその背景には、「正しくありたい」という真面目さやこだわりも見え隠れしていて、複雑な気持ちになります。
45分座るのはつらい。でも工夫がいっぱい
1限45分の座学はやっぱりしんどい。
でも、その中でも「黒板に答えを書きに行く時間」を作ったり、「かるた」や「クイズ形式」で遊びを交えた学習を取り入れてくれているそうです。
支援級ならではの柔軟さと工夫に感謝。
情報が多いと混乱しちゃう
たとえば、「プリントやって、丸付けして、◯分までに先生に出してね」
これって大人からすれば簡単な流れに聞こえますが、次男にとっては…
- プリントをやる
- 丸つけをする
- 時計を見て時間を意識する
- 提出する
この「4つの動作」が重なると混乱のもとになる。
だから、一つずつ指示を出すこと、大きなビジュアル時計を使うこと、声かけでフォローすることが実践されていました。
「できる範囲で大丈夫」——手厚い配慮に感謝
学校ではトイレの失敗は今はないけど、給食で苦手なものが出ると不安でトイレにこもろうとする場面もあるそうです。
でも交流級の子たちも優しく、ケンカしながらも自然と関われていて、人間関係の中で育まれる学びもちゃんとあることがうれしかったです。
夏休みのドリルと、最後に夫が投げかけた質問
もうすぐ夏休み。
「夏のドリル」は、みんなと同じ量は難しいからと、減らした課題と“できたらでいいよ”ページを先生が用意してくれました。
中には、なぞり線や、書きやすいように円や補助線がたっぷり書き足されていて、
その手厚さに「ありがたいなぁ…」としみじみ。
「じゃあ、今日はこれで」と思ったそのとき、隣の夫が口を開きました。
「この子の将来、どうでしょう?」
「うちの子は料理が好き。小さい子の世話も好きで、将来は料理人か保育士になりたいって言ってます。どうでしょうか?」
……えっ。
私は一瞬、心の中で「そんな未来のこと聞く!?」って思ってしまった。
けど同時に、
「私は“今”ばかり見てたけど、夫は“将来”を見てたんだ」
ということにハッとさせられました。
先生は、少し間を置いて、こんなふうに答えてくれました。
「今の様子を見ながら、ゆっくり学習していきましょう。料理人なら、修行を積んだり経験を積む中で道が開けるかもしれない。保育士は資格が必要なので、本人のやる気や学習の伸び具合によると思います。将来的には、障害者雇用のある会社に入る可能性もあるかもしれませんね」
「障害者雇用」——その言葉に、心が揺れた
その言葉を聞いて、私はちょっと衝撃を受けました。
頭のどこかで「そのうち周りに追いつくかも」と思っていた自分に気づいてしまったんです。
「この子はこの子なりに育っていく」
そうわかっていたはずなのに、どこかで“いつかは…”と期待していた自分。
そして「定型発達の子との差が縮まらないかもしれない」と気づいた瞬間、思ったよりショックを受けている自分にも驚きました。
それでも。気づけたことに感謝したい
だけど、未来のことを真剣に考えてくれていた夫にも、
答えにくい質問に誠実に返してくれた先生にも、感謝の気持ちでいっぱいです。
きっと、どんな道を選ぶにしても、親が“今”だけじゃなく“これから”も一緒に見てあげることが必要なんだと思います。
次男のこと。
“できるようになる”ことだけを目指すんじゃなくて、
“その子なりに育っていく道を一緒に探す”というスタンスで、これからも寄り添っていきたいです。
わが家でもビジュアル時計を取り入れてみました
ちなみに余談ですが、ビジュアル時計、学校で使われていたのはものすごく大きかったです。
でも視覚的にとてもわかりやすかったので、わが家でも導入してみました。
実は「砂時計タイプ」もかわいくて惹かれたんですが、うちはシンプルな時計型のものにしました◎
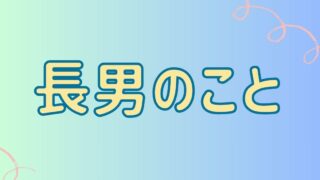

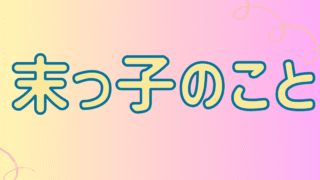

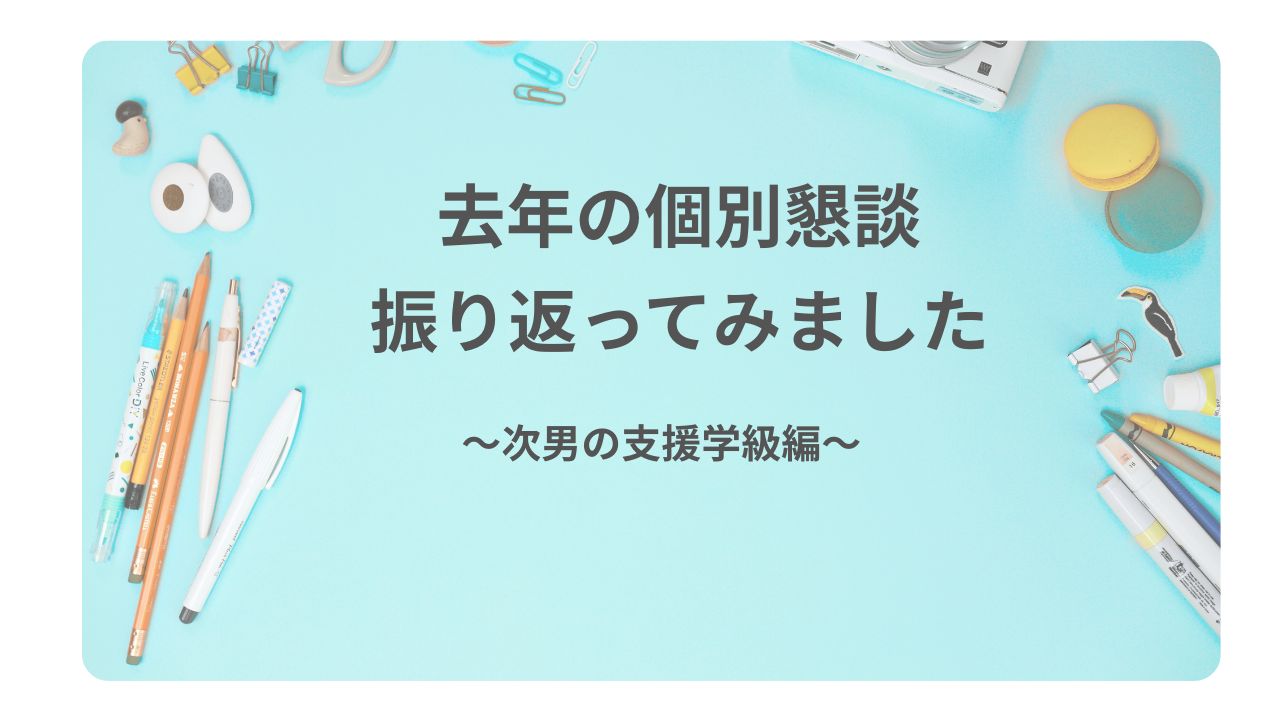
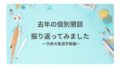
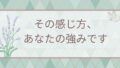
コメント